交通事故でむち打ちになった場合、「慰謝料として、いくらもらえるのか?」は、多くの被害者が抱える疑問です。
実は、むち打ち慰謝料の金額は、算定基準や後遺障害の有無によって大きく異なります。
本記事では、≪むち打ちの慰謝料相場≫・≪計算方法≫、≪増額するためのポイント≫などを、交通事故(被害者側)の賠償請求に豊富な解決実績を有する弁護士が詳しく解説します。
不当に低い金額で示談しないために—。
交通事故によって、むち打ちとなった方に知っていただきたい内容となっています。是非、ご確認ください。

もくじ
むち打ちで受け取れる慰謝料の種類 |
そもそも慰謝料とは、精神的な苦痛を補償するための賠償金です。
交通事故によるむち打ちで受け取れる慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。順にご説明します。
① 入通院慰謝料 |
入通院慰謝料とは、ケガが原因で入・通院を強いられたことに伴う精神的な苦痛を補償するための賠償金です。
つまり、交通事故によるケガが原因で入院・通院をしていれば、入通院慰謝料を受け取ることができます。この慰謝料の額は、入通院の期間や日数に応じて変わります。
② 後遺障害慰謝料 |
後遺障害慰謝料とは、交通事故の影響で障害が残ったことに伴う精神的な苦痛を補償するための賠償金です。この後遺障害慰謝料を受け取ることができるのは、後遺障害等級が認定されたケースに限られます。
一般的に、治療をしても事故前の状態へ完全に戻っていないときには、「後遺症が残った。」と表現する場合があります。しかし、交通事故における後遺障害が認定されるには、一定の基準を満たさなければなりません。
つまり、「後遺症」が残っていても、「後遺障害」と認定されない場合には、原則として、後遺障害慰謝料を受け取ることができません。
交通事故における後遺障害には、1級から14級の等級が定められており、数字が小さい方が障害の程度が重くなります。そして、等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額は変わります。
むち打ちの場合には、12級あるいは14級が認定される可能性があり、後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料を受け取れる可能性が出てきます。

むち打ち慰謝料の相場
|
交通事故における慰謝料は、「誰が算定するか」によって金額が異なります。具体的には「自賠責基準」・「任意保険基準」・「弁護士基準」と呼ばれる3つの基準が存在します。
ここでは、基準ごとの慰謝料相場を見ていきましょう。
① 3つの基準の違い |
3つの基準の意味は、それぞれ次のとおりです。
| 自賠責基準 | 自賠責保険における支払い基準。3つの基準の中で最低額。 |
| 任意保険基準 | 任意保険会社が会社ごとに定める基準。自賠責基準に多少の上乗せをした程度の金額が一般的。 |
| 弁護士基準 | 弁護士が請求する際の基準。過去の裁判例をもとにしており、3つの基準の中で最高額。 |
任意保険基準は、保険会社ごとに異なり、公開されていません。任意保険基準による金額は、自賠責基準から多少の上乗せをした程度となります。
金額の高さの順番は、「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」となります。
以下では、自賠責基準と弁護士基準における慰謝料の相場をご紹介します。
② 入通院慰謝料の相場 |
自賠責基準では、入通院慰謝料を「4300円×対象日数」で計算します。
「対象日数」は、「通院期間(治療期間)」と「実通院日数(実際に病院に行った日数)×2」のうち、いずれか少ない方を採用することになります。
たとえば、通院期間150日、実通院日数30日のときは、「実通院日数×2(=60日)」の方が少ないです。したがって、対象日数は60日となるため、自賠責基準による入通院慰謝料は、「4300円×60日=25万8000円」と計算できます。
一方で、弁護士基準では、むち打ちの入通院慰謝料を基本的に通院期間によって決定します。
弁護士基準による、むち打ちの場合の入通院慰謝料は、次のとおりです。
|
通院期間 |
入通院慰謝料 |
|
1ヶ月 |
19万円 |
|
2ヶ月 |
36万円 |
|
3ヶ月 |
53万円 |
|
4ヶ月 |
67万円 |
|
5ヶ月 |
79万円 |
|
6ヶ月 |
89万円 |
|
7ヶ月 |
97万円 |
|
8ヶ月 |
103万円 |
|
9ヶ月 |
109万円 |
|
10ヶ月 |
113万円 |
|
11ヶ月 |
117万円 |
|
12ヶ月 |
119万円 |
通院を頻繁にして、自賠責基準で計算した金額が大きくなりやすいケースでも、一般的には弁護士基準の方が高額となります。
たとえば、通院期間1ヶ月(30日)で実通院日数が15日だと、対象日数が30日となるので、自賠責基準での入通院慰謝料は「4300円×30日=12万9000円」となります。したがって、弁護士基準での入通院慰謝料である19万円の方が高いです。
③ 後遺障害慰謝料の相場 |
後遺障害慰謝料は、等級ごとに異なります。
むち打ちで認定される可能性がある12級と14級において、後遺障害慰謝料の相場は、次のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
いずれの等級でも、弁護士基準は自賠責基準の3倍程度です。
このように弁護士基準の方が、大幅に高いことがお分かりいただけたことでしょう。
④ 弁護士基準が最も高い理由 |
弁護士基準は、過去の裁判例をもとにした金額であり、自賠責基準や任意保険基準と比べて高額となっています。
そもそも自賠責保険は、強制加入保険であり、最低限の補償をすることを目的にしています。自賠責基準が低額なのは、ある意味当然といえるでしょう。
任意保険基準が低額なのは、保険会社が営利企業であるためです。一定の利益を上げる必要がある以上、支払額を可能な限り抑えようとします。「法律に精通していない被害者が応じてくれればよい。」と考え、低い金額を提示するのです。
「被害者自身で交渉するときも弁護士基準で請求すればいいのではないか?」とお考えの方もいるでしょう。
しかし、実際には、被害者本人との交渉において、相手方は、弁護士基準での支払いには応じてくれません。
訴訟で裁判所に認められれば弁護士基準で支払いを受けられるものの、被害者が自力で訴訟までするのはハードルが高いためです。
弁護士が入って慰謝料を請求する際は、訴訟も辞さない姿勢で交渉にのぞみます。
実際に訴訟提起も現実味が高まるため、相手方も「裁判になるぐらいなら、請求額に近い金額で解決しよう。」と考えやすいです。
したがって、弁護士は、裁判で認められるであろう、高額な慰謝料を交渉段階から請求できるのです。
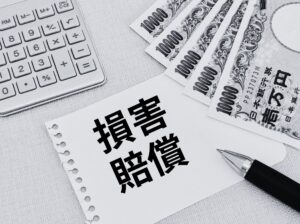
慰謝料を増額するためのポイント |
むち打ちで慰謝料を増額するためには、以下の点を頭に入れておきましょう。
① 後遺障害等級の認定を受ける |
後遺障害の等級認定を受けられると、後遺障害慰謝料が発生するため、慰謝料を大幅に増額できます。
むち打ちの後遺障害認定を受けるためには、まずは必要な検査を受けるのが重要です。
具体的には、MRI等の画像検査、神経学的検査が挙げられます。
むち打ちでは客観的な証明が難しいケースも多いです。そこで、自覚症状を医師へ正確に伝え、「後遺障害診断書」へ反映してもらうのもポイントとなります。
また、後遺障害認定に当たっては、次に紹介する通院頻度・期間も大切な要素になります。
| むち打ちの後遺障害に関する詳細は、「むち打ちの症状が長引くときに知っておきたい後遺障害等級のポイントを徹底解説」もご覧ください。 |
② 適切な頻度で必要な通院をする |
慰謝料を増額するには、通院頻度も重要です。通院頻度は、少なすぎても多すぎてもいけません。
通院頻度があまりに少ないと(例:月1回)、通院期間が短いものとみなされ、入通院慰謝料が低額となるリスクが高いです。また、後遺障害の認定にあたっても、通院頻度が少ないと「症状が軽いもの。」と判断され、マイナスの方向に働きます。
とはいえ、必要以上に高頻度で通院すると(例:毎日)、「治療の必要性がなく、治療費は支払わない。」と主張されるおそれがあります。
医師や弁護士と相談したうえで、適切な頻度(例:週2~3日)で通院するようにしてください。
③ 通院期間も慰謝料に大きな影響を与えます |
弁護士基準による入通院慰謝料は、原則として、完治あるいは症状固定までの通院期間に応じて決まります。
症状固定とは、「それ以上治療を続けても症状が改善しない状態」を意味します。
この症状固定に関する時期の判断は、医師の見解が重視されます。しかし、相手方の保険会社が早い時期に治療費の支払い打ち切りを宣告してくるケースがあります。
安易に応じて、本来の症状固定時期よりも前に治療をやめてしまうと、症状が改善されないばかりか、入通院慰謝料の対象となる期間が短くなり、慰謝料額が少なくなってしまいます。
また、通院期間は、後遺障害認定にあたっても重要です。むち打ちの場合には、一般的に通院期間が6ヶ月未満だと後遺障害が認定されないケースが多くなります。症状固定前に治療を途中でやめてしまうと、本来認定されるべき等級が認定されず、後遺障害慰謝料を受け取れないおそれがあります。
慰謝料のためだけに治療を長引かせることは避けるべきですが、本来の症状固定まで治療を続けることが、適正な慰謝料を支払ってもらうためのポイントになります。
④ 弁護士に依頼する |
慰謝料を増額するには、弁護士への依頼がオススメです。依頼するメリットとしては、以下の点が挙げられます。
| 〇弁護士基準で慰謝料を請求できる。 |
|
〇治療中から通院に関するアドバイス等のサポートを受けられる。 |
|
〇後遺障害の認定手続きを代行してもらい、認定可能性を高められる。 |
|
〇相手方との交渉や訴訟対応を任せられるため、精神的な負担が軽減される。 |
| その他、交通事故被害に関して弁護士に依頼するメリット等については、「交通事故の被害に遭ったら...。弁護士に相談すると何が変わるの?」もご覧ください。 |
むち打ちで慰謝料を請求する流れ |
実際に慰謝料を請求するまでは、以下の流れで進みます。
① 完治または症状固定まで治療する |
交通事故でむち打ちになった場合、まずは、完治または症状固定まで治療を続けます。
一般的に、むち打ちの治療期間は、3~6ヶ月程度です。ただし、症状によって異なるため、医師や弁護士と相談し、適切な頻度で、必要な期間を通院しましょう。
先ほど説明したとおり、通院頻度や期間は慰謝料請求にあたって重要です。
② 必要に応じて後遺障害を申請する |
完治せずに症状が残った場合、後遺障害の申請を検討します。
申請には、相手方保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、自身で手続きをする「被害者請求」という2つの方法があります。
認定にプラスとなる資料を自ら添付できるため、被害者請求の方が認定可能性を高めやすいです。
むち打ちでは、申請後2~3ヶ月以内に結果が出るケースがほとんどです。結果に納得がいかないときは、異議申し立て手続きもできます。
| 異議申立てを実施した結果、むち打ちの後遺障害が認定された解決事例は、「こちら」をご覧ください。 |
③ 交渉または裁判で慰謝料を請求する |
後遺障害の申請をしなかった場合、あるいは申請を経て結果が確定した場合には、相手方との示談交渉に移り、慰謝料を請求します。
交渉で合意できないときは、訴訟等の法的手段を用います。
適性な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼したうえで、弁護士基準で請求するのがオススメです。

まとめ — 泣き寝入りをせず、まずは弁護士にご相談を — |
ここまで、むち打ちの慰謝料について、相場や増額のためのポイントなどを解説してきました。
① むち打ちの慰謝料とは?受け取れる2種類の補償 |
交通事故によるむち打ちで請求できる慰謝料は、大きく次の2種類です。
| ①入通院慰謝料 |
| 【対象】治療のために入院・通院したことによる精神的苦痛。 |
| 【ポイント】通院期間や日数に応じて、金額が決定。 |
| ②後遺障害慰謝料 |
| 【対象】事故の影響で後遺障害が残った場合の精神的苦痛。 |
| 【ポイント】後遺障害等級の認定が必要。むち打ちでは12級または14級が認定される可能性。 |
② むち打ち慰謝料の基準 |
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額は、どの基準で算定するかによって異なります(通常は、自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準です。)。
高額な慰謝料を受け取るには、弁護士基準での請求がベストです。
| 自賠責基準 | 最低限の補償。最も低額。 |
| 任意保険基準 | 自賠責基準より少し高いが、保険会社が独自設定。 |
| 弁護士基準 | 裁判例に基づく最も高額な基準。 |
③ むち打ち慰謝料を増額するためのポイント |
|
① 後遺障害等級の認定を受ける |
〇MRI・神経学的検査など証拠を早期に確保。 〇医師に症状を正確に伝え、診断書に反映してもらう。 |
|
② 通院期間・頻度を適切に管理する |
〇通院が少なすぎると「症状が軽い。」と判断され減額リスク。 〇逆に多すぎると「治療不要」とされる場合も。 〇週2〜3回程度で症状固定まで治療継続が理想。 |
|
③ 弁護士に依頼する |
〇弁護士基準での請求が可能。 〇後遺障害認定のサポートが受けられる。 〇相手との交渉・訴訟対応を任せられ、精神的負担も軽減。 |
④ むち打ち慰謝料請求の流れ |
| ①完治または症状固定まで治療する ⇓ ②必要に応じて後遺障害を申請 ⇓ ③示談交渉または訴訟で慰謝料を請求 |
⑤ 最後に |
以上までのとおり、交通事故によるむち打ちの慰謝料は、算定基準によって数倍の差が生じることがあります。
自賠責基準では最低限の補償しか得られず、任意保険基準も保険会社側の都合で低額に抑えられる傾向があります。
一方、弁護士基準を用いた請求では、裁判例に基づく適正な金額を得られる可能性が高くなります。しかし、この基準での交渉は、被害者自身では困難であり、専門知識と法的交渉力を持つ弁護士のサポートが不可欠です。
また、通院の仕方や後遺障害等級認定の準備など、初期対応の一つひとつが慰謝料額を大きく左右します。治療中の段階から弁護士に相談することで、適切な証拠収集や交渉方針を立てることが可能になり、結果的に高額な慰謝料につながります。
湊第一法律事務所では、交通事故被害者の方を多数サポートし、後遺障害認定や交渉による慰謝料増額で豊富な実績を有しています。事務員任せにせず、弁護士が直接対応し、あなたの状況に合わせた最善の解決策を提案しますので、安心してご相談・ご依頼ください。
初回相談は無料です。どんな小さな悩み・疑問でも構いません。交通事故でむち打ちになった方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿日:2025年8月6日
更新日:2025年8月19日
【この記事の監修弁護士】
 |
弁護士 國田 修平 依頼者と「協働する姿勢」と、法律用語を平易に伝える対話力に定評がある弁護士。 |
<略歴>
愛媛県出身。明治大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
全国展開の弁護士法人に入社し、2年目には当時最年少で所長弁護士に就任。その後、関東に拠点を移し、パートナー弁護士として、組織運営や危機管理対応、事務局教育などに携わる。労働法務・社内規程整備などの企業法務から、交通事故・相続・離婚・労働事件といった個人の法律問題まで幅広く対応。中でも、交通事故(被害者側)の損害賠償請求分野では、850件の解決実績を有する。
弁護士業務の傍ら、母校・明治大学法学部で司法試験予備試験対策講座の講師も務め、次世代を担う法曹育成にも力を注いでいる。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・債権回収
・交通事故などの損害賠償請求事件
・労働事件(労使双方)
